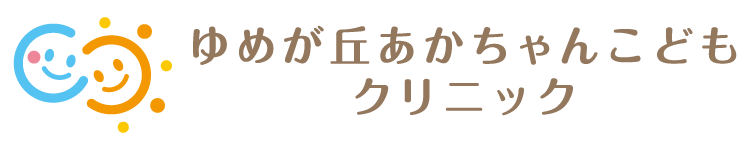インフルエンザ
インフルエンザとは
インフルエンザは、インフルエンザウイルス(A型、B型、C型など)に感染することで発症します。ウイルスは、感染者の咳やくしゃみなどの飛沫によって空気感染したり、ウイルスが付着した物に触れた手で口や鼻を触ることで接触感染したりします。特徴的なのは、急激な発症です。数時間から1日ほどで、38℃以上の高熱、悪寒、全身倦怠感、頭痛といった症状が現れます。ウイルスは複数種類存在し、一度感染しても、別の型に感染する可能性があります。そのため、毎年流行するのです。インフルエンザの重症化は、乳幼児や高齢者、基礎疾患を持つ方において特に注意が必要です。お子さんの場合、高熱による熱性けいれんやインフルエンザ脳症といった重篤な合併症のリスクも考慮しなければなりません。
インフルエンザの症状
インフルエンザの症状は、主に以下のものです。
- 38℃以上の高熱
- 激しい悪寒
- 全身の倦怠感
- 頭痛
- 咳
- 鼻水・鼻づまり
- 喉の痛み
これ以外にも筋肉痛や関節痛、嘔吐や下痢といった消化器症状が現れることもあります。乳幼児では、高熱による熱性けいれんや脱水症状に注意が必要です。また、インフルエンザは肺炎や気管支炎などの合併症を引き起こす可能性もあるため、注意深く観察することが大切です。症状の持続期間は、通常数日ですが、高熱が5日以上続く、呼吸が苦しい、意識が朦朧としているといった場合は、すぐに小児科を受診しましょう。
インフルエンザの原因
インフルエンザの原因は、前述の通りインフルエンザウイルスです。A型、B型、そしてまれにC型ウイルスが原因となりますが、毎年流行するウイルス型は異なります。そのため、過去にインフルエンザにかかったことがあるお子さんでも、再度感染する可能性があります。
かぜ(風邪)の治療
インフルエンザの治療は、主に症状を抑える対症療法と、ウイルス増殖を抑える抗インフルエンザ薬の投与です。高熱には解熱剤を使用しますが、アセチルサリチル酸(アスピリン)は、小児レイ症候群のリスクがあるため、お子様には使用できません。咳や痰には鎮咳去痰薬を使用します。十分な休養と水分補給も重要です。脱水症状を防ぐために、経口補水液やスポーツドリンクなどをこまめに飲ませましょう。抗インフルエンザ薬は、ウイルス増殖を抑制し、症状の軽減や回復期間の短縮に効果があります。しかし、抗インフルエンザ薬は、発症後早期に服用を開始することが重要で、症状が出てから48時間以内が理想とされています。医師の指示に従って正しく服用しましょう。
ご家庭での注意点
インフルエンザは、周囲への感染拡大にも注意が必要です。感染者は、発症後5日間はウイルスを排出するため、マスクの着用、咳エチケット(咳やくしゃみをする際は、ティッシュや肘で口と鼻を覆う)、こまめな手洗い・うがいが重要です。家族内での感染を防ぐため、食器やタオルなどの共用は避けましょう。また、重症化しやすい乳幼児や高齢者と同居している場合は、特に注意が必要です。早めの受診と適切な治療によって、重症化を防ぎましょう。インフルエンザの予防には、ワクチン接種も有効です。毎年秋に接種することで、感染リスクを軽減できます。
登園・登校の目安
お子様がインフルエンザにかかった場合、保育園や学校への登園・登校は、発症後5日を経過し、解熱後2〜3日経過してからにしましょう。ただし、医師の判断に従うことが重要です。